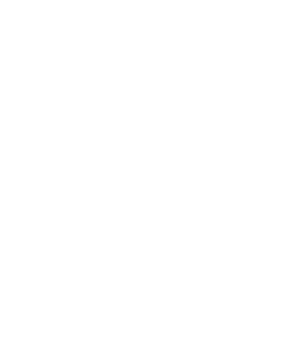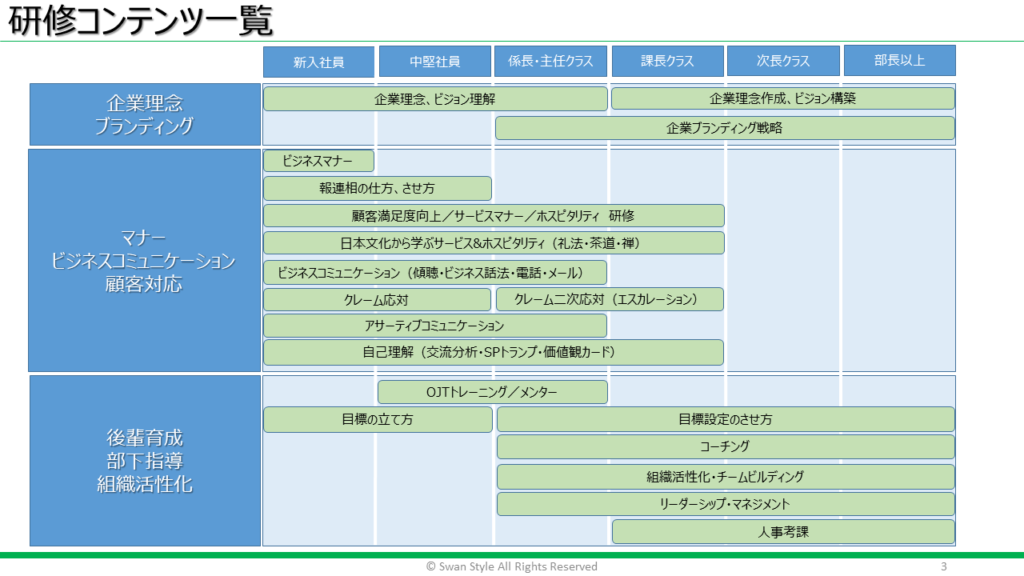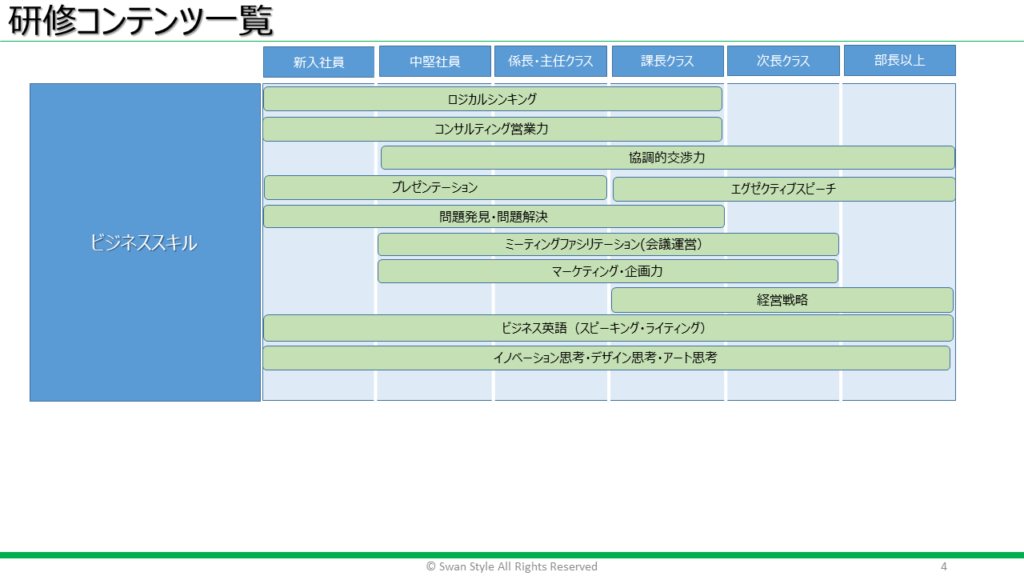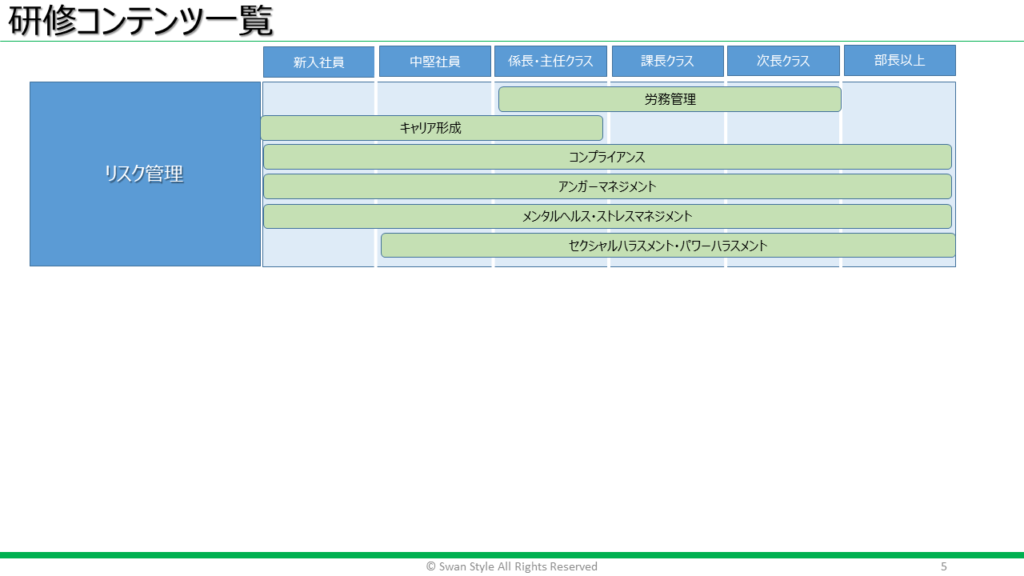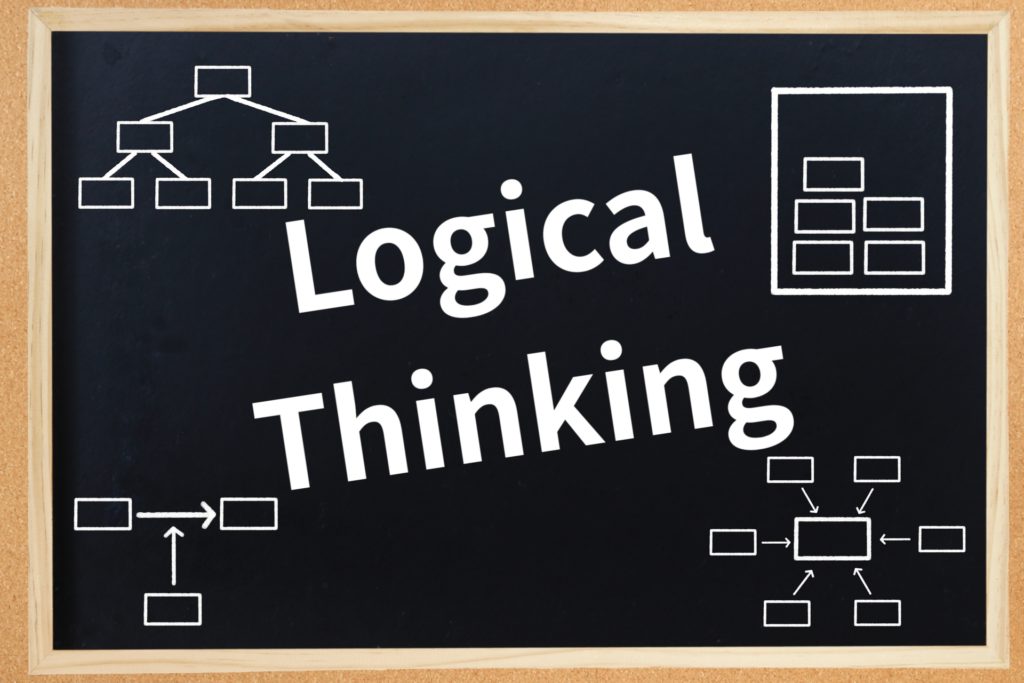コンパッションに必要な5つ資質 ~エッジステートメント~
2021年02月27日
今回は「コンパッション」の概要です。
◆エッジステートメント~5つの資質~
第一人者であるハリファックス老師は
著書の中で
コンパッションを発揮するために必要な資質として
この5つを挙げています。
※説明を一部平易な言葉に置き換えました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、利他性
他者のために役立ちたいという気持ちを自然にもち
無欲で行動に移せること
2、共感
他者の感情を自分のフィルターを通さずに
感じ取ろうとすること
3、誠実
人として正しいと思える指針を持ち
それに一致した言動をとること
4、敬意
相手の立場に関わらずその存在を尊重し
発生した出来事を受け止めること
5、関与
誠意をもって全力で関わり取り組むが
一定の距離を持ち続けること
そして必要な時がきたら手放すこと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これらの資質は
「エッジステートメント」と呼ばれ
これを高めると
山頂のような素晴らしい景色が見える場所に
立つことができます。
例えば
お客さまのお困りごとを全力で解決したとき
「これからはほかの人ではなく、あなたにお願いしたい」
と言われ、心の底から
‘この仕事を選んでよかった’ と
思ったことがあるのではないでしょうか。
また、お客さまはもちろんのこと
仲間との何気ない会話から
温かさや心の落ちつきを感じたこともあるでしょう。
一方で
この資質の使い方を誤ると
山頂の端(エッジ)滑り落ち
望まない状況が生まれてしまうのです。
◆エッジステートメントの影
1、利他性
褒められたいからやる=承認欲求に捉われてしまう
過剰な手助けにより相手を依存させてしまう
2、共感
相手の感情(悲しみや怒り)と一体化しすぎて
自分も傷ついてしまう
3、誠実
理不尽なことや忖度など
正義感に反する行為を目にしたり
関わらなければならないときに苦しむ
4、敬意
自身の価値観と異なる相手を
否定し、貶めたり心の中で嘲笑する
5、関与
過剰な心理的・肉体的負荷により疲弊する
達成感の欠如や無力感に伴う意欲喪失、燃え尽きる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
思い当たることはありませんか?
サービス&ホスピタリティには
誰もが納得する正解や
これで終わりというゴールはありません。
相手を思っての行動だったのにそれを否定されると
山頂がわからなくなったり
崖から突き落とされたような気持ちになります。
心が優しい人だからこそ疲れてしまう
頑張ってきた人ほど燃え尽きてしまう
サービス&ホスピタリティ産業の影とも言えるでしょう。
ではどうしたらよいのでしょうか?
◆コンパッションの影から抜け出すために
「優しい心さえあれば
どんな時でも人に寄り添える」
それは成り立たない世の中になりました。
光が強ければ、影も濃くなるように
高い志=コンパッションを持つ人ほど
崖から滑り落ちることが多いものです。
だからこそ、準備をしましょう。
一つは
崖から落ちても、もう一度山頂を目指そうと思える
しなやかな回復力=レジリエンスを備えましょう。
もう一つは
崖から落ちないようバランスを保つための
トレーニングをしましょう。
次回は、そのトレーニング方法をお伝えします。
カテゴリ:スキルアップコラム