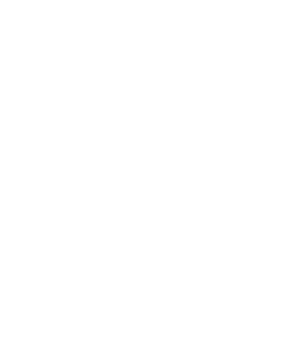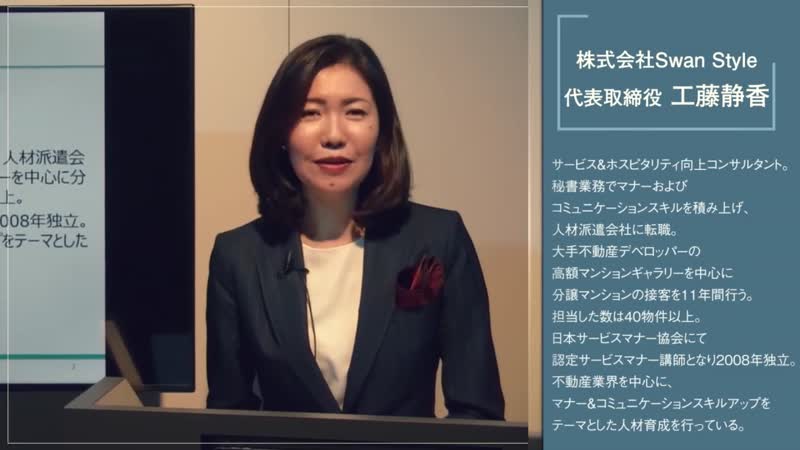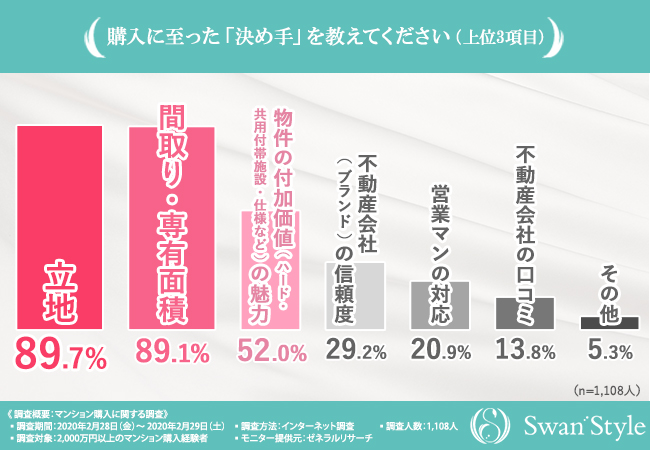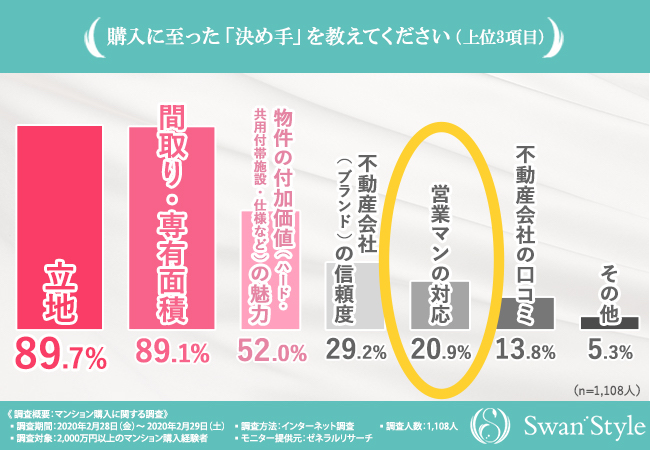♯ハラスメント パワハラと言われないために〜アサーティブなコミュニケーションとは
2020年04月03日
こんにちは。
ブログ担当の出澤です。
パワハラが大きな社会問題になっている中、いわゆる「パワハラ防止法」も成立し、社員の指導や研修に力を入れている企業が増えています。一方、「これを言ったらパワハラになるのではないか」と、部下の指導法について悩んでいる管理職者も少なくないようです。
そこで今回は、そもそもパワハラとはどういうことなのか?
パワハラ社員にならないためのコミュニケーションのポイントをご紹介します。
1.パワハラは〇〇〇と同じです!
パワハラ社員にならないために、まずは「パワハラとは何か?」をきちんと理解しておく必要があります。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)では、以下3つを満たすものを「パワハラ」と定義しています。
(1) 優越的な関係を背景とした
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
(3) 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
わかりやすく言うと「地位や職権を利用して仕事の範囲を超えた嫌がらせをすること」で、「学校」が「会社」に変わっただけで、いわゆる「いじめ」です。学校でのいじめと同じく、加害者が意識的に行っている場合もありますが、無自覚のうちに相手を傷つけている場合もあるので注意が必要です。
子どもには「いじめはよくないこと」だと教えている大人が、会社の中ではいじめをしているとしたら、恥ずかしいことですよね。
では、パワハラ社員にならないために、どのようなことに気を付けたらいいのでしょうか?
2.アイデアや力の掛け算が生まれる「アサーティブなコミュニケーション」
そのヒントとなるのが「アサーティなブコミュニケーション」です。
「アサーティブ(assertive)」とは「自己主張すること」ですが、この場合の自己主張とは、自分の考えを一方的に述べるのではなく、相手を尊重しながら適切な方法で伝えることを示します。
つまり、「自分も相手も尊重したコミュニケーション」が「アサーティブなコミュニケーション」なのです。
パワハラコミュニケーションでは、相手から強引に「YES」を奪おうとしますが、アサーティブなコミュニケーションでは、両者のアイデアや力の掛け算の成果が生まれ、相互の信頼関係も深まります。
具体的には、以下の例の×ではなく〇のようなコミュニケーションを心掛けるとよいでしょう。
1)意見を述べるとき
×自分の意見ばかり述べる
×相手を否定する
×まわりくどくて抽象的な表現
〇要点がわかりやすい
〇自分の意見と事実を分けて伝える
2)相手へのフィードバック
×批判、否定が多い
×反応しない
〇相手の「人格」ではなく「行動」について建設的な批判や賞賛を伝える
3)話を聞くとき
×話を聞かない
×話の腰を折る
〇熱心に反応しながら聞く
〇相手の話を引き出す
4)相手がミスをしたとき
×「全然なってない」「ミスが多い」などあいまいな表現
×人格を否定する
〇「納期が〇日遅れている」など、事実で叱る
〇解決するためにサポートする
5)自分がミスをしたとき
×なかったことにする。ミスを隠す
×他社に責任を転嫁する
〇スピーディに謝る
いかがでしたか?
「上司だから」「部下だから」と、立場の上下をつけるのではなく、お互いを尊重しながら、チームのミッションに向けてリソースを最大に発揮するためにも、アサーティブなコミュニケーションを心がけましょう。
カテゴリ:スキルアップコラム