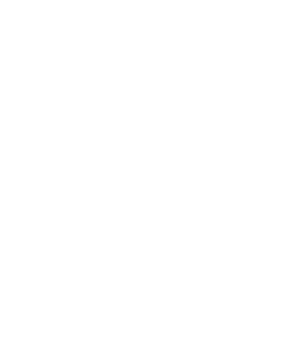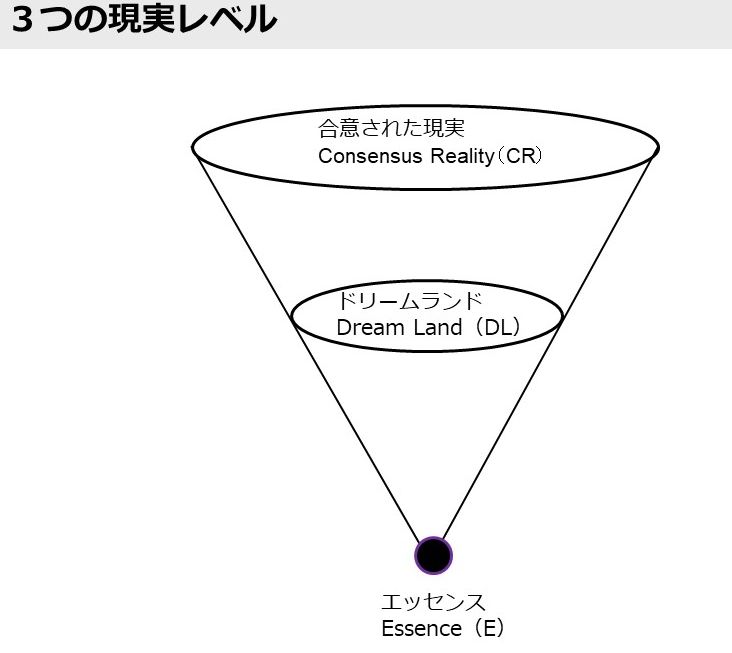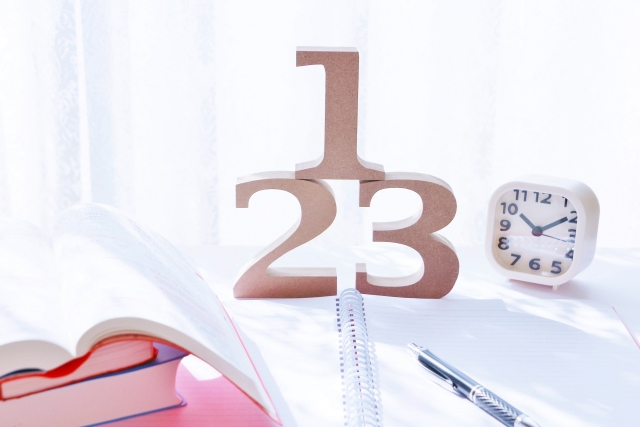#組織開発2 ダンスフロアに降りてみる
2020年06月01日
こんにちは、工藤です。
今期前半の学びのテーマ
「組織開発 Organization Development」
講座提供元(バランスドグロースコンサルティング様)の
許可をいただき
内容の一部をシェアしていきます。
::::::::::::::::::::::::::::::
◆実施したワークショップ
第二回講座では
企業の実例を取り上げ、ケース分析を行いました。
(非常にリアルで良くも悪くも生々しい)
具体的には
・バルコニーから見る(全体を俯瞰する)
・ダンスフロアに降りる(自分の足で踊る)
このようなことをします。
個人的には
「バルコニービュー」
「ダンスフロア」
という言葉が素敵だな、とおもいました。
だって
オペラやミュージカルみたいじゃありません?
どんなことするんだろう!
楽しみ!
とワクワクしていました。
しかし、それは見事に裏切られます。
さて、ダンスフロアでは
A:社内変革推進派「変わろう」
B:社内保守派 「今のままでいい」
という
ロール(役割)を設定し
それぞれになりきって
心の声を言葉にしてみました。
最初はおっかなびっくりでしたが
少しずつメンバーが声に出しはじめ
ちょっと感情的な声色が表れると
一気にリアル感が高まりました。
「全員一言は言葉にしましょう」
ファシリテーターの促しがありましたが
実は、私は声を出せませんでした。
◆やってみてどうだったか?
※個人的な感想です。
B(保守派)のロールになったとき
本当にしんどかったです。
思うことはあるのですが
声に出せないのです。
身体も重くなるし
力が入らない。
例えると
拗ねた子供のような
そんな気持ちになっていました。
そしてずっと考えていました。
私はコンサルタントという職業上
変化を導入する側=Aです。
それゆえ
Bの気持ちや声を
受け止めることが大切であると
大事だとわかっていたし
それを心掛けていたつもりだったのですが
私がロールで感じたような
これほどの無力感や疎外感を
Bが味わっていたのだとしたら・・・
本当に受け止めていたのだろうか?
講座がクローズしたあとも
そんな衝撃を
ずっと引きずっていました。
◆心理学的に解説
(講座提供元の解説を要約)
このワークでは
相手の声を内側から聞く体験をしました。
(ポジションスイッチによる認知の変化)
それにより
・相手(時に対立相手)のアイデンティティへの理解拡大
・IからWeへの意識の拡大
・相手のエゴや恐れを理解する
そんな変化が起こります。
これを
「相手と自由にダンスを踊れる状態」
というそうです。
◆組織開発ではどこに作用するのか?
何かを変えようと思うと
必ず抵抗=壁がありますよね。
(私は実務で山のように経験しています。)
その壁を超えるためには
抵抗感情への理解が必須。
このワークはそのプロセスの一つかな、と。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の場合
相手の感情が
生々しいリアル感を伴って
流れ込んできたので
抵抗感情への理解が感じられたのですが
人は
深い感情やエゴにアクセスしないよう
無意識にコントロールしているそうです。
企業でこのようなワークを行うとしたら
無意識のブロックを外せるような
本人の心の準備
安心安全な環境整備
ファシリテーターとの信頼関係構築
がキモになると思いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感情への理解がすすんで
お互いが相手のエゴや恐れを感じることができると
IからWeへ視点の統合が始まります。
この時から
「ではどうすべきか?」
という真に建設的な話し合いの段階に進みます。
(建設的なフリではなくなるのですね。)
◆まとめ
「相手を理解する」
という言葉がありますが
それは
「相手の感情を理解する」
ということなのかもしれません。
今回の体験で
相手の感情を「真」に理解するのは
本当に難しい、と痛感しました。
言葉にするとシンプルなのですが
「心から理解しようとする」
これが第一歩です。
その気持ちが伝わると
相手との関係性=組織の対立構造が
無意識のうちに
変化するのかもしれません。
カテゴリ:スキルアップコラム